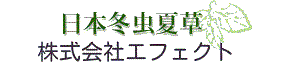◆前立腺がん(前立腺癌)
前立腺は膀胱の下にある男性にだけある臓器で前立腺液を分泌し精液の一部を作る臓器です。
前立腺にできる悪性腫瘍の事を前立腺がんといい、欧米では非常に多いがんです。
日本でも社会の高齢化や食生活の欧米化に伴い前立腺がんの発生は増加傾向にあります。
50歳代から増え始め70歳代、80歳代と発生率は増えていきます。
前立腺がんは1993年の米国では成人男性に発生するがんのうち第一位の発生率で死亡率は肺がんに次いで2番目となっています。
日本でも今後ますます前立腺癌の発生は増加していくことが予想されています。
前立腺がんは成長速度がおそく、発がんしてから臨床がんになるまでに40年近くかかると推定されています。
すなわち、青壮年期にがん細胞が発生し、20~30年経って微少がんとなり、その後数年以上経って臨床がんに成長すると考えられます。
前立腺がんは早期のうちに発見できれば直る率も高くなります。
簡単な血液検査で前立腺癌の疑いがあるかを調べることができるので、50歳以上の男性は定期的に前立腺癌の検査を受けることをお勧めいたします。
【前立腺がんの原因】
前立腺がんの発生は老化による性ホルモンのバランスのくずれが影響していると考えられています。
実際に前立腺癌の発生は50歳以上から増え始め高齢になるほど多くなります。したがって高齢者は前立腺がんになる可能性が高いといえます。
男性の平均年齢が上がればそれだけ前立腺癌の患者さんも増えることになります。
他に食生活の欧米化により、動物性脂肪や動物性タンパク質の摂取量が増えたこと、繊維質やビタミンAの摂取量が減っていることも影響していると考えられています。
【前立腺がんの症状】
前立腺は男子の膀胱の出口、尿道のはじまりの部分を取り囲むクルミ大の臓器です。
尿道に接する内側の部分を内線、外側の部分を外線とよびますが、前立腺がんのほとんどは外線にできます。
一方、高齢者に多い前立腺肥大は内線にできます。
前立腺がんは外線にできるためすぐに尿道を圧迫することがなく、早期のうちにはほとんど症状がありません。
がんが大きくなって尿道や膀胱を圧迫するようになると排尿に関連したさまざまな症状が見られるようになります。
例えば尿が出にくくなったり、尿がでるのに時間が掛かる排尿困難や尿の回数が特に夜間に増える頻尿、排尿後でも尿が残っている感じがする残尿感、尿の勢いが弱い尿線無力などの症状です。
ただし、これらの症状は前立腺肥大症でも起こる症状であり、症状だけでは前立腺癌と区別することはできません。
さらにがんが大きくなり尿道を強くあっパックするようになると排尿困難が進み、膀胱に尿が溜まっても排尿できなくなる尿閉が起こるようになります。
また、尿道や膀胱内に浸潤した場合にはその部分が出血し血尿が見られることもあります。
膀胱にがんが進むと失禁になります。尿管が詰まる閉塞状態になると腎臓で作られた尿が膀胱まで流れなくなり腎臓に溜まるようになるため水腎症になり背中に痛みを感じることがあります。
前立腺癌は骨、特に背骨や腰椎、骨盤に転移しやすく足腰が痛むようになりひどい場合には歩行困難にまでなることがあります。
骨転移を起こした部位の骨が弱くなるため骨折もしやすくなります。
またリンパ節にも転移しやすく、その場合にはリンパ節に疼痛や張り(腫張)が見られ、下半身に浮腫みが現れることもあります。
自覚症状が出たときには既にがんが進行している事が多いため、50歳を過ぎたら泌尿器科で年一回は前立腺がんの検査を行う事をお勧めいたします。
【前立腺がんの診断】
前立腺がんの検査には次のものがあります。
直腸指診は前立腺がんの検査で従来より行われている方法です。
肛門から直腸の中に指を入れて、直腸の壁越しに前立腺の大きさや形、硬さ、周囲との境界、痛みの有無などの状態を調べる検査です。
がんが進行している場合には前立腺は硬くなり、周囲の組織との境目が不明瞭になってきます。炎症が起きている場合には痛みも伴います。
直腸指診はPSAの検査で数値が高めであった場合に行われることが多くなってきました。
PSAの検査で数値が高めの場合に行われる検査で、前立腺の場合の超音波検査は肛門から超音波発信器を入れて直腸を通して前立腺の状態を調べる経直腸的超音波検査が行われます。
正常な前立腺は左右対称で、周囲との境界もはっきりしていますが、がんになると左右非対称になったりいびつな形になったり、境界が不明瞭になります。
直腸診では分からない前立腺の内部の状態を画像で確認することが出来ます。
上記検査でがんの疑いがあれば針生検を行い前立腺癌の確定診断が行われます。
経直腸的超音波検査で前立腺の位置を確認しながら針を刺して組織を採取し顕微鏡で検査を行い、がんの拡がり具合、がんの悪性度などを判断します。
以上の検査で前立腺癌が確定した場合にはがんがどこまで拡がっているのかを調べることになります。
CT検査(CTスキャン)はいろいろな角度から体内の詳細な画像を連続的に撮影しコンピュータを使って非常に鮮明な画像を得ることができます。 周囲の臓器やリンパ節転移の有無を調べることができ癌の進行具合を調べるためには重要な検査になります。
MRI検査は磁場を使っていろいろな角度から体内の詳細な画像を連続的に撮影する検査です。
放射線の被曝がなく超音波検査では見分けの付きにくいがんもMRI検査で診断できる場合があります。
前立腺がんは骨に転移しやすいので、骨転移の有無・位置を知るために アイソトープ(骨転移のある部分に集まる物質)を注射して2~3時間後、特殊なカメラで全身の骨を検査します。
がんが骨に転移した場合にはALPの数値が異常に高くなります。
1980年代に発見された前立腺がんの腫瘍マーカーPSAは前立腺癌の早期発見に大いに貢献しています。
他の多くの腫瘍マーカーは複数のがんに反応したり、初期には数値の上昇がないことがありますが、PSAは前立腺の異常だけに敏感に反応します。
前立腺癌の実に90%程度がこのPSAの検査で見つかっている画期的な検査方法です。
がんの進行とともにPSA値も上昇するため病期(ステージ)も予測することができます。
ただし、前立腺肥大症や前立腺炎でも上昇することがあるためPSA値だけではがんの確定診断はできません。
前立腺がんの治療
前立腺がんの治療には「ホルモン療法」、「外科療法(手術)」、「放射線療法」が行われるのが一般的です。
他に「化学療法(抗がん剤)」もあります。
治療法は、がんの進み具合(病期)やがんの部位、患者さんの年齢などから判断されます。
前立腺がんの病期(ステージ)はがん細胞の異型度(悪性度)を5段階で判断するグリーソン分類やリンパ節転移の有無や遠隔転移の有無などを確認することで判断します。
| A期 |
前立腺肥大症に対する手術の結果、偶然発見されたがん |
|---|---|
| B期 |
がんが前立腺内に限局する状態 |
| C期 |
がんが前立腺の被膜を超えて周囲脂肪組織、精嚢もしくは膀胱頚部に浸潤している状態 |
| D期 |
がんがリンパ節や骨、肺、肝などの遠隔臓器に転移している状態 |
前立腺がんの異型度(悪性度)は高分化型がん(おとなしいがん)、中分化型がん、低分化型がん(悪性度の高いがん)がどの程度を占めるかによって判断されます。
主たる(最も大きな領域を占める組織評価)評点(1-5)と従たる(大きな領域を占める組織の評価)評点(1-5)によって,その分類評価は2(極めて高分化=悪性度が低い)から10(極めて低分化=悪性度が高い)までスコアがつけられます。
前立腺がんの治療-経過観察
前立腺癌は、前立腺肥大症などのほかの病気を手術した際に発見されることがあります。
また、高齢者でPSA値や画像検査で前立腺がんの疑いがあり、生検をしたところがんが発見されることがあります。
これらの初期のがんで悪性度(異型度)が低いおとなしいがんは「偶発がん」といわれ、グリーソン分類では3以下のがんになります。
この場合にはすぐに治療を行うのではなく、定期的にPSA値の測定をし変化を見ていきます。
PSA値の変動がない場合にはがんが成長していないと考えられるため、そのまま経過観察をします。
PSA値が上昇するようであれば必要に応じて治療を開始します。
前立腺がんの治療-ホルモン療法
ホルモン療法は、前立腺がんの治療として最も基本となる治療法です。
前立腺癌の成長には男性ホルモンが関与しています。そのため男性ホルモンの作用を抑えてがんの勢いを弱めようという治療がホルモン療法になります。
ホルモン療法はがんが限局していなくても行うことができるためどの病期でも治療が行えます。
以前は精巣摘出術といって男性ホルモンを分泌する精巣を切除する方法が取られていましたが、最近は、LH-RHアゴニストという注射を使うことで精巣を切除するのと同等の効果が得られるため精巣切除は減ってきています。
脳の下垂体はLH-RHというホルモンの刺激を受けて精巣や副腎から男性ホルモンを分泌させるホルモンをだします。
LH-RHアゴニストを注射しはじめると最初は急激に男性ホルモンが分泌されますが、やがて下垂体が反応しなくなり男性ホルモンの分泌が低下します。この皮下注射を1ヶ月~3ヶ月に一度行います。
ゾラデックスやリュープリンが使われます。副作用ではほてりや発汗などがあります。
このLH-RHアゴニストに加えて男性ホルモンの分泌を抑える女性ホルモン薬(エストロゲン)を使うか、男性ホルモンが前立腺に働きかけるのを防ぐ抗男性ホルモン薬(アンチアンドロゲン)を内服で使います。
女性ホルモン薬には(エストラサイト、ビアセチル、プロエスタ)やホンバンがあります。
副作用で特に注意が必要なのは血栓や心筋梗塞・心不全で、胸部痛、手足の浮腫み、動悸・息切れ、立ちくらみ、手足のしびれなどが出た場合には致命傷になることがあるためすぐに対応する必要があります。
抗男性ホルモン薬にはステロイド性の薬と非ステロイド性の薬があります。
ステロイド性の抗男性ホルモン薬にはプレドニゾロン(プレドニゾロン、プレドニン)、デキサメタゾン(デカドロン、デキサメサゾン、ミタゾーン、コルソン)などの薬があります。
非ステロイド性の薬にはカソデックス、オダイン、プロスタールなどの薬があります。
これらの薬の副作用には過敏症、悪心、嘔吐、呼吸困難、女性化乳房および肝機能障害がみられることがあります。
ホルモン療法を長く続けていると効果がなくなってくるため、できるだけ長期にわたって効果を持続させるために薬を使わない時期を設ける「間欠療法」が行われるようになってきました。
PSAの数値が下がったらホルモン剤の投与を一度休止し、上昇してきた場合に再び使い始めるといいうもので、副作用を軽減し、効果を長続きさせられるといわれています。
前立腺がんの治療-外科手術療法
転移のない前立腺がんに対しては前立腺を全て摘出する前立腺全摘除術が行われることがあります。
前立腺および精巣を摘出するとともに周囲のリンパ節の切除も行い、その後膀胱と尿道をつなぎ合わせます。
この方法は目に見えるがんを全て切除する方法ですが、前立腺内に限局している場合しか対象にはならず、目に見えない小さな浸潤や転移が取り残される可能性があります。
浸潤や転移の可能性がある場合にはホルモン療法や放射線療法が術後に行われることがあります。
ホルモン療法が長期にわたると効果がなくなってくるため、早期がんであれば切除することが多くなります。
しかし、手術の後遺症として尿失禁とED(性機能不全)が起こる可能性があります。
前立腺がんの治療-放射線療法
放射線療法は高エネルギーの放射線を使ってがん細胞を殺す治療方法です。
放射線をあてる方法には外部照射(体の外から前立腺をねらってあてる)・術中照射(おなかを開いている間に病巣にあてる)・組織内照射(がんに針を刺し、その先端からあてる)があります。
放射線療法の副作用には治療中又は治療直後にでるものと、半年~数年後にでてくる晩期合併症とがあります。
放射線の照射量には決まりがあり、無理をして大量の放射線照射を行うと強い副作用が出る可能性が高いため注意が必要です。
しかし最近の外部照射では放射線装置の進歩により副作用の割合もすくなく、安全性も増してきています。
また、将来的に新しい照射法「小線源刺入法(しょうせんげんしにゅうほう)」が保険適用されれば、治療用の放射性物質をがん内部に埋め込むことで、正常組織への放射線の影響を最小限に抑えることができ、がんに対しては常時放射線治療を行えるようになります。
(現在日本では放射性物質の取り扱いの規制上、認可されていません)アメリカでは小線源刺入法が、早期前立腺がんで活動的な多くの患者さんにすでに使用されています。
前立腺がんの治療-化学療法
前立腺癌に対して抗がん剤療法はそれほど効果が認められていないため通常は行われません。
ホルモン療法が有効で無い場合や効果がなくなった場合に抗がん剤治療が行われています。
【前立腺がんの治療-緩和ケア】
骨に転移すると痛みが出てきます。
この痛みを緩和するために最初のうちはボルタレンなどの非モルヒネ系のクスリを使いますがそれで抑えられなくなるとMSコンチンやカディアンなどのモルヒネを使うか、フェンタニル(デュロテップパッチ)という貼り薬(麻薬)を使う場合もあります。
放射線療法や抗がん剤を用いた化学療法では白血球減少による免疫力の低下が起こりやすいため体を清潔に保つことが大切ですし、規則正しい生活を送る必要があります。
免疫力を賦活させることが大切です。
また、骨髄損傷による白血球減少、血小板減少、貧血などが起こりやすいため造血機能を強化することも大切になります。