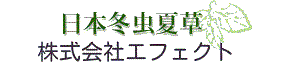◆腎臓がん
腎臓は体内の老廃物や余分な水分、塩分などを尿として排出し、エリスロポエチンという造血ホルモンを分泌する事で骨髄の赤血球生産を促し、骨の成分であるカルシウムを骨に沈着させる時に必要な活性ビタミンD3の生産を行っています。
腎がん(腎癌)は腎臓の中の多くは尿細管の上皮細胞から発生します。
腎臓はそら豆のような形をしていて、重さ130g、直径11~12cm程で、肋骨に上半分を守られるように背中側に左右に2つが副腎と共に脂肪に包まれています。
腎がん10万人当たりの発生率が男性で7人、女性で3人程度で、40歳以上から発生しやすくなる腫瘍です。
腎臓がんの発がん要因は、腎不全、喫煙、性ホルモン、高血圧、肥満などが挙げられます。
また、常染色体優性遺伝であるvon Hippel-Lindau病(フォン・ヒッペル・リンドウ病)との関連性があり、腎がんの中で最も多い明細胞がんでは染色体の欠損がしばしば認められます。
腎臓がんには明細胞がんの他に乳頭状がん、嫌色素性細胞がん、集合管がんなどの組織型があります。
腎がん(腎癌)の症状
腎臓がんは無症状で見つかる事が多い。 微熱、食欲不振、貧血など。
腎臓がんは進行するまでは自覚症状に乏しく症状による早期発見が難しいがんです。
症状が進行すると血尿、腹部のしこり、疼痛、微熱、食欲不振、貧血などの症状が現れます。
現在は、画像診断が発達したため、無症状で偶然見つかる腎がんが、全体の半分以上を占めています。
このため早期発見のためには、定期的に検査で腹部超音波を受ける事が大切になります。
腎がん(腎癌)の診断
腎がんの発見に有用な腫瘍マーカーはなく、診断は画像検査が中心です。
身体的な負担がほとんど無く、簡便な検査法のため、スクリーニングとして非常に有効です。
また、肝臓や胆のうなどを調べる場合でも、腹部超音波検査が行われます。
ことのきに、腎臓が画像に移るため、偶然腎がんを発見するケースが多いのです。
超音波検査でがんが疑われる場合、CT検査、またはMRI検査で確定診断をつけるというのが、現在の標準的な診断法で、鑑別診断にも有用です。
腎臓の周囲が広い範囲で見えるMRI検査のほか、血管の様子が鮮明に映る三次元CT検査やMRA検査は、手術方針を立てるのに有効です。
腎がんは、転移が多いので、転移のチェックも行われます。
肺の検査には、エックス線検査や肺CT検査が行われ、特に肺CT検査は微小な病変の発見に有効です。
骨への転移は、骨と反応する放射性医薬品を体内に注入して撮影する「骨シンチグラフィー」で診断します。
このほか、血管内に細い管を通して、造影剤を使って撮影する「血管造影検査」が行われることもあります。
しかし、CTやMRI検査で同様の情報が得られるため、行われる頻度は少なくなっています。
腎がんの治療
腎がんの治療は「外科療法(手術)」が中心となります。
他に「免疫療法」、「化学療法(抗がん剤)」があり、がんの進行度(病期:ステージ。下記表参照)や患者さんの全身状態を考慮して治療法が選択されます。
腎がんのTMN分類(1999年)
| T原発腫瘍 | |
|---|---|
| TX |
原発腫瘍の評価ができない |
| T0 |
原発腫瘍を認められない |
| T1 |
原発腫瘍が7.0cm以下で、腎臓に留まっている |
| T1a |
原発腫瘍が4.0cm以下 |
| T1b |
原発腫瘍が4.0cm以上かつ7.0cm以下 |
| T2 |
原発腫瘍が7cm以上で、腎臓に留まっている |
| T2a |
原発腫瘍が7.0cm以上かつ10.0cm以下 |
| T2b |
原発腫瘍が10.0cm以上 |
| T3 |
癌細胞が腎静脈または腎周囲組織に浸潤して骨筋膜に留まっており、同側の副腎おらず同側の副腎への浸潤が見られない |
| T3a |
腎静脈に目視可能なほど浸潤している、または腎周辺に浸潤が見られるが骨筋膜に留まっている |
| T3b |
腎静脈または横隔膜下までの下大静脈内に目視可能なほど浸潤している |
| T3c |
横隔膜を越える下大静脈内に目視可能なほど浸潤している |
| T4 |
骨筋膜を超えて浸潤している |
| N所属リンパ節 | |
|---|---|
| NX |
所属リンパ節への転移評価ができない |
| N0 |
所属リンパ節への転移が認められない |
| N1 |
1箇所の所属リンパ節への転移が認められる |
| N2 |
2箇所以上の所属リンパ節への転移が認められる |
| M遠隔転移 | |
|---|---|
| M0 |
遠隔転移なし |
| M1 |
遠隔転移あり |
| 病期(ステージ)分類 | |||
|---|---|---|---|
| 病期(ステージ) | 原発腫瘍 | 所属リンパ節転移 | 遠隔転移 |
| Ⅰ期 | 腫瘍径7cm以下 |
無 |
無 |
| Ⅱ期 | 腫瘍径7cm超 |
無 |
無 |
| Ⅱ期 | 腎臓内に留まっている |
1箇所 |
無 |
腎臓周囲に進展 (骨筋膜を超えない) |
1箇所以下 |
無 |
|
| Ⅳ期 | 骨筋膜を超えて浸潤している |
不問 |
無 |
不問 |
2箇所以上 |
無 |
|
不問 |
不問 |
有 |
|
治療の中心は、手術療法です。
小さい腎がんでは、腎臓全体を切除する方法から、患部とその周辺を小さく切除する方法へと移行しつつあります。
通常、入院は10日間程度です。
腎がんの治療 外科手術
がんのある腎臓全てと、腎臓の上部にある副腎や腎臓周囲の脂肪などを一緒に取り除く手術です。
ただ、副腎は摘出してもしなくても、治療成績は変らないというデータもあります。
腎臓は左右にあるので、片側の腎臓を摘出しても、反対側の腎臓が正常に働いていれば、機能的には問題はありません。
しかし、がんでないほうの腎臓の機能が悪いときには、がんのある腎臓(患側腎)の機能を残すことが必要になります。
そこで最近は、がんとその周辺だけを切除して、腎臓の機能を温存する「患側腎温存手術」が行われるようになっています。
一般に直径3cm以下で、無症状のがんに適応されます。
切除方法はいくつかありますが、日本で開発された「マイクロ波組織凝固器」を利用した方法が簡便で普及しています。
側腹部を切除して、超音波画像でがんの位置を確認しながら、マイクロ波を出す針をがんの周囲に直接刺して、凝固します。
その後、凝固した部分を切開して、がんを切除します。
出血も少なく、手術時間は3時間ほどで、肝機能への影響もほとんどありません。
最近では一部の医療機関で、腹腔鏡を用いて行われるようになり、患者さんの身体的負担の軽い治療法として、期待されています。
がんが多発していたり、再発したときには、次のような治療が必要になります。
腎がんの治療 免疫療法
がん細胞を攻撃する、体内の免疫機能を強化する治療法です。
現在、標準的に行われているのは、免疫系の細胞を活性化する、「インターフェロン」を注射する方法です。
15~20%ほどの患者さんに、がんが半分以下に縮小する効果が見られます。
インターフェロン単独では効果のない人には、「テセロイキン(インターロイキン-2剤)」が併用されます。
そのほか、ワクチンを利用した「免疫ワクチン療法」なども研究されています。
異物が体に入ると、体内ではそれに対抗するため、特殊なタンパク質(抗体)をつくり、異物を攻撃します。(免疫)
「ワクチン」は、このシステムを利用し、病原体の一部、または類似したものを人工的に体内に入れて抗体をつくり、病気を予防する方法です。
これと同じように、異物であるがん細胞の一部を体内に入れて、免疫に関わる細胞を活性化することでがんを攻撃させようとする治療法が「免疫ワクチン療法」です。
さまざまながんで研究が進められていますが、ワクチンは、その患者さんの組織のタイプに適合しないと効果がありません。
腎がんでは日本人の40%程度に適合するワクチンが開発されました。
2002年5月から、奈良県立医科大学付属病院で臨床試験が始まっており、さらなる研究が期待されています。
腎がんの治療 化学療法
腎臓は、体内の不要な物質を排出する機能があるため、抗がん剤が効きにくく、化学療法が単独で行われることはあまりありません。
ただ、「フルオロウラシル」などの抗がん剤や、胃潰瘍などに用いられる「シメチジン」と、インターフェロンを併用する「多剤併用免疫化学療法」が一部で行われています。
上積み効果が期待されており、現在、その有効性が検討されています。
なお、放射線療法は、腎がんではあまり効果がなく、骨転移の痛みの緩和など、限られたケースでのみ行われています。